
海とカモメの夜に あなたが私の元に戻ったら あなたの目尻に キスしてみよう あなたの嘆き、 失われた浜の 虚空と唇の疑わしさは 私の口を乾ききらす
詩のカテゴリ:

海とカモメの夜に あなたが私の元に戻ったら あなたの目尻に キスしてみよう あなたの嘆き、 失われた浜の 虚空と唇の疑わしさは 私の口を乾ききらす

二人には七夜だけだったかも わからない 数えていなかったから 或いは少なくとも六と言おうか ひょっとすると九 わからない でもそれらは私の宝物 一番長い愛だった 多分 四夜か五夜ほどだったか 正確にはそれくらいか 多分 それだけで生きられた 人生で思い切り 大きな愛

音もたてずに 雪の一ひらのように クリスマスが来た 夜が交わるところで 静寂の静止と合流した 旅に疲れても 腹を空かせた子供に母乳を与えた その神聖な夕べは 人々の客だった 奇跡を携えるクリスマスは 長く留まらなかった、 希望と歌が 詰まった袋をとじて、去った 皮肉だけ 持ちされなかった 飾りの一つとして クリスマスツリーの枝に掛けられた

もし生まれ変わるなら、ここへ戻して もしも生まれ変わるなら、ここへ戻して. . . 同じ門をくぐり戻るのでしょうか 同じ雫を 同じ虹を 同じ町に流れ着く 同じ荒れた小川を見れるのでしょうか?
同じ花は咲くのでしょうか 同じ蜂が蜜を吸い、 私の望みを知り 蜂蜜を作るのでしょうか 私の心はまた山を登り 興奮を廻らせ 喜びを基礎にした 同じ苦しみで 家を立てるのでしょうか?

眼は精神の入り口である。 だから今、知恵を働かせるため、閉じた方がいい 日々を冷淡に進める⋯
そして心のドア⋯耳; 知恵を働かせるため、耳も閉じよう 亡き人のため、老人のために祈ろう
彼らは愛されるべきである 少しの愛、生命の保証、 法やお触れは必要ない
白痴で心なしに生きるより 最小限の生命のかけらでいたい

訪ねた私を迎える 大きく手を広げた母 来れないという電話に応えた時の 優しい言葉の母 話をしたくても、もうできなかった 顔を横に向けた母 最後の挨拶に遅すぎて着いた時の 目を閉じた母

彼の瞳と彼女の泪の間は いつもそのスーツケースと 数え切れない旅行による遠距離がある
洞察に至るまで 詩の火に至るまで 異国において

このもつれた世界の 秩序は保たれていると 自らを欺き 信じ込ませる
飢えた子供が 泣いているのが 聞こえる
死んでいく兵士が 見える
地球の心が 縮こまっているのを 感じる

彼らは必要のないものを売る それでも君は買う 彼らは好きでない耳障りな歌を歌う それでも君は聴く
花々のささやきは いつ聞くのか?
外見のきらびやかさを押付け 同様になるため 彼らから奪い取ろうとする 脳から理論を搾り取る 彼らを真似したら 己を高めてくれると君は信じる
鳥たちのさえずりは いつ聞くのか?

マリア・ミラーリアへ
薄暗い夕方に 疲れ果てた鳥が虚しく 眠る場所を探している時に 君に愛の詩を詠もう
月の灯火が 夜に微光を捧げる時 君に愛の詩を詠もう
太陽が夜明けの希望を 赤色に染める時 君に愛の詩を詠もう
心が皺寄り顔でも 優しい風が撫でる時 君に愛の詩を詠もう
上空の高い高い所で 二つの雲が 愛のキスで抱擁する時 君に愛の詩を詠もう

来るな、死神よ、まだ来るな 望む地へ辿り着く為 長い梯子を登らなくてはならない まだ法の真理に辿り着いていない せねば、せねば、ここで成すべき事がある。
借りがあるから返さなければいけない 影の様に通り過ぎるより何かの為にここにいる 私の中から現れようとしている光がある まだ来るな、時間を与えよ、私に

喜びの中 自己を追究する
すぐに 終わりを迎える
憂鬱は 遅々と 薄れていく
自己を追究する 言葉の中に 自己を見出す

アルトゥーロ・コルクエラ氏を悼んで
時間は数字で飾られ進む 〜ルイス・デ・ゴンゴラ〜
尖ったくちばしの鳥、その時計の分針 まるでハチドリ 白磁の平面を回転、壁に囚われている 二針目が後を追う、むしられた雛鳥のよう 共に、ローマ数字を羽織り、時間を指し示す。 人間の心臓のように、 生涯は過ぎ脈拍は低下すると 告げている。

無音の 彼女の細いシルエットは 床に触れない
浮かび アンクレットだけが 優雅な歩みに反して鳴る
(目を閉じる)
彼女がスペインのジプシー酒場にあらわれて 純白のソレアを ギターのブラシ演奏で情熱的に踊る
情熱、誘惑と色彩が渦巻き 眼も心も盲目に
裸足のダンスに 木のフロアさえ願望で震える
彼女の足踏み、スキップ、漂い 深紅のドレスを左へ振り、また右へ ちらほら一見を露にする
—それだけ—
夢でさえも見せない

月が御手伝いさんを呼んで 暗黒の円蓋に 輝く真珠を留めるとき 私に愛の詩を詠んで
風が優しく 樹々の樹上を揺さぶり ロマンチックな小夜曲を奏でるとき 私に愛の詩を詠んで
波が曙光の中 喜びあふれる子供達のように 追いかけっこをするとき 私に愛の言葉を詠んで
伝達鳥のように 窓辺にやってきて 歌を歌い あなたについて話してくれる ひよことスズメたちに 世界で最も美しい愛の韻をささやいて
朝霧が どこまでも続く草原の まだ眠そうな花々を 軽く優しく目覚めさせるとき 私に世界で一番甘い愛の言葉を集めて
地平線の太陽が 果てしない抱擁で 海にキスをするとき それからまた愛の言葉を私に詠んで

無風 何度も何度も懇願してきた そしていつも怒り狂う顔を 見てきた
これが最後だ 私の手を取り 国境まで 運んでほしいと 懇願する しかし国境警備隊へ 引き渡さないでほしい 我らのオリーブの樹々の間の ハンモックのところへ 寝かせてほしい なだめ 口笛の 子守唄を。

ジャーメイン・ドルーゲンブロート氏へ捧げる
他銀河より 降りかかる 人工的な イタカの太陽
光で 囲まれた 白い円形のよう
夜に ゴーストたちの ひとつが魂を 浪費したよう
神が、 無意識に、 夜明けで作った 楽園

ピーター・ヘルトリング氏を悼んで
今は、私の物語に 文章はもう 舞い降りない。 今は話し、今は 自ら呼吸する、 今は、私から 消え去る世界に、今は 私は存在する、 己を忘れ、 今は青ざめる かつての文章 今は、捨てられる名前 そしてもう 今は存在しない

君の笑顔は 庭全体を輝かせるなんて もちろん大げさだけど 本当に見たんだ 君が近づき 一つ花が咲いたのを

素肌を目覚めさせ 繰り返し満たすその接触で 生き返らせるその言葉を 君は気にいるでしょう
瞳に瞳を感じられること 腕に腕を感じられること 灰色のアスファルトの道を 昼の疲れた光の中歩くこと
それぞれの夜明けに戻り 記憶の差の間の失われた瞬間を見つける それらの旅行の繰返しを気にいるでしょう
それぞれの瞬間の呼吸を感じさせ 呼吸するその空間に入らせるその言葉を 君は気にいるでしょう

昼のうちに 心に落ちた詩を 夕刻に書く。 道を歩く 人々の詩。 船乗りと 売春婦の詩。 正午の広場での 犬の詩。 生きることの 石、パン、団結の しがらみが 夜に重くのしかかる。 そして、 労働者の手に書く そして恋人たちの 瞳について書く。 そして、夕刻に、太陽の下に 雨の日に書く。 そして、書く。

細かく引き裂かれあまりに無駄な 塩で焦がした数え切れない日々、 その直後の永久的な写真、 もし遅すぎなければ、 私の体内の状態を推測できた 私の身体の刺青は異国の地の太陽の様に輝く。 浴室の死んだ幾つもの星 海の底の棘を探しに行き あなたを許してあげられた。 無限を断ち切り、壁に貼付け、 待ち、惑星たちがぶつかり合う事を願えた。
そしてなんでもない事で壊れた この些細な事にどれだけ犠牲を払ったのか あなたへ電話して伝えられた。

かつてなく、わたしたち自身の写真を撮る。
お互いに肩組をして いつも笑顔で 絶えず幸せの様子
永遠に続くのかもしれないと 見事な姿勢で自身を写し込む。
でもその写真に 心を埋め込めたら どうなるだろう?

リリアンへ
手が どれほど寂しいか 心が どれほど思慕しているか 不意に気づく時
意識的だったのかどうか 置き去りにした 場所や時間に どう帰ろう
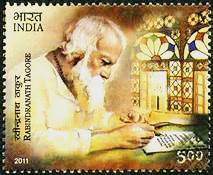
君の眠りの 夢の戸口で 窓に映るような明けの明星が 君の顔に現れるのを静かに見つめて待つ。 海辺で 東に眼を凝らし 恍惚状態で不寝の番の時間を過ごし、 明け方の光に 浸かるのを楽しみにしている 瞑想する修行者のように。
私の眼で 少し開いた君の唇に花が開く 君の最初の笑顔を飲むんだ まるで花の蕾、 それが私の願い。

問題はこのように解決されると思っていた。 真夜中に来ないであろう最終バスを 駅で待つ人々の集団のように 最初の数人から、どんどん増える。 お互いに仲良くなり 共に全てを変えられ 新しい世界を始められる機会だった。
しかし散りじりに。 (恩寵の時は過ぎた。もう再び 起こらない。)それぞれが己の道を行く。 おのおのはまた 片面を上にしたドミノになり 繰り返し続くゲームで 合致するもう1片を探す

その時その時に 愛は特有の ことばを持つ 例えば、私の肩に寄り添う あなたのこめかみの柔らかい軽さや あなたのドレスが滑り落ちる その速さ

行かないで欲しいかのように 私の足元に降着するまで 川や人々の流れを越え いくつもの寺や城を通り過ぎ 民主制のように飛ぶための 羽を欲しがる私の思想を ついばむ鳥達に 何を言いましょう

かつて蝶であったのかな
産まれる前 木であったか 星であったか
もう忘れてしまった
でもわかることは かつてそうであったように 未来にも私は存在する
永遠の中の 瞬きの一瞬に

詩心は 家に窓があるように 自然的
窓硝子のように 人工的
窓の向こう側の世界のように 偶発的
科学のように 論理的
知識獲得と 喪失の 接点にあるようだ

何時でも舞い戻り私を抱きしめて 身体の記憶が目覚め 昔の憧れで再び血が騒ぎ始める時 唇と肌が思い出し この手でまるで触れているかのように感じる時 愛おしい感覚が戻り私を包み込む
唇と肌が思い出したら、 夜に、何時でも舞い戻り私を抱きしめて

貴方が守ってくれる魔法の場所へ のがれる 愛する人よ
草たちも お辞儀する 生きている森で
それは この上なく美しいもの

星を見つめていた 夜が明けるまで 朝の曙色で、夜の虹彩が閉じた
今見た夢は ただの夢でなく
バラの葉脈の 脈相は
未来を物語る

私は砂漠の砂 渇いた砂漠 君の唇はオアシス 私の飲めない所にある
唇:オアシスは受け入れる 砂漠のすべての砂を
枯渇した世界の 真ん中の湿ったところ 君の身体、君の身体は もう二度と二人のものとならない
身体:渇きと太陽で枯渇した私を潤した 井戸は閉じた


その人は朝に泣き 昼に泣き 夕方に泣いた 朝、息子を失い 昼、もう一人の息子を失い 夕方、最後の家族を失った 翌朝、人々はその人のために泣き 昼にその人々のために別の人々が泣き 夜には泣き声は聞こえなくなった 街中が血の海だった

毎日 仕事へ行く 妻、オルガのため オルガが買物するに足る金を持てるよう
どうにかしないといけない 週末が近い 日曜日、子供達は食べたいだろう 私たちはこの悪習を 打ち破れずにいる

ねえ、 あなたはこれまでになかった と言う あの夜以上に幸福であったことはないと 決して! 私にそう言った その瞬間に 伝えないと決めたの 自分自身を欺いたのか けれどたぶん 確かに想う あの夜は わたしの人生で最も美しい夜

コンスタンスは筆をとった
果物や野菜が表紙の スケッチブック
さくらんぼを緑色に 塗りつけ バナナは青色に
レタスにおいては黄金色で まるで天国を探しているような筆使い
そして私は想う あまりに現実的でやつれ果ててしまっている 大人たちを

守護者に なれる ように あなたの喜びを 預けてください
祈りが 聞こえる 惑星を 周回し 星屑に しています
風の中 散りじりの マントラが 共鳴する時 黄金の穂が 落ちて
そして喜びが 舞い戻る
パンの 香りに
猫が目を開けて 太陽が入った 猫が目を閉じて 太陽は留まった
ほら、だから夜に 猫が目を覚ました時 暗闇の中に見える 太陽のかけらが二つ

バレンタインデーの日に
満たされた 記憶の中の 目には見えないページ
暗号化され 他の誰も 解読できない
いく度もいく度も 書きなおされた
こころの中の 粘土板

熱い それは恋
愛へ向け ひた走る
とはいえすべての航行が 抱擁が 待っている 桟橋にはたどりつかない
毎晩 難破船があり
毎朝 浜へ 集められる
沈んだ船体と あふれる 想いが

ひとりぼっち 澱んだ湖は みるみるうちに縮む
きみは岩 鈍い響きをたてる
でもきみは愛しいひと 溺れさせることを 抑えられない

ある時には 至極やさしい ひとことが 欲しい たったひとこと 寒さに耐え 恐怖に耐えられる ひとことが 私を暖め 息苦しさから開放する 重さのないひとこと 平和のひとつぶだけ 背負おう 瞬く間に 飛び去ってしまわないように

ルビーを見つけた 折り重なった石の中で 珍しく光り輝いていた 単なる小石ですよ と、専門家は言う 単なる小石でも 何か特別なものになりたい 原子の唯一の塊 産業の堆積物 何万もの波の数が仕上げた「磨かれた技」 選ばれたと 見て、感じて 何か特別なものになりたい

未来に何が 待ち受けているのか
さらなる戦争 毒ある野望を持つ国々の さりげない会話 哀れな政治家たちよ どこからどこへ向かうというのか 答えはない 一瞬で 高く登ったキノコ雲は 全てを燃え尽くす

ひとみの中の きらめく月光
優しくなでる風 ある時はひとこと
手でつつみこむ 抱擁のような
やさしい光 私の心にたいせつなもの